【熱性けいれん】1歳児が夜中に意識を失ってけいれんした夜の話
① パパとママの会話|「これ、救急車呼ぶやつ…?」
ママ:ねえ、あの夜のこと覚えてる?長女が1歳5ヶ月のとき、夜中に急にけいれんして…。
パパ:あのとき、俺当直だったよね。電話でママが「意識ない!けいれんしてる!」って泣きそうな声で言ってて、すごく焦った。
ママ:夕方から少し熱があって、まあ大丈夫かなって思ってたら、夜中に急に体が熱くなって、体温測ったら41度。ぐったり寝てたと思ったら、急に痙攣しだして。目も合わないし、声かけても反応ないし…。
パパ:それはほんと怖かったと思う…。でも、救急搬送してもらって、診断は「熱性けいれん」だったよね。
ママ:そのとき初めて「熱性けいれん」って言葉をちゃんと意識した気がする。でも、何をどう判断して、どう対応したらよかったのか全然わかんなかった…。
② パパの勉強メモ|「熱性けいれん(熱性発作)について」
● 呼び方とその背景
医学的には「熱性けいれん」と「熱性発作」という言葉が併用されています。英語では“febrile seizure”という用語が使われますが、日本の最新のガイドラインでは「熱性けいれん(熱性発作)」と表記されています。
「けいれん」というと、手足のガクガクした動き(convulsion)を連想しがちですが、実際には非けいれん性の発作(脱力、一点凝視、眼球上転のみなど)も含まれます。誤解を避けるため、「発作(seizure)」を併記しています。
● 定義と対象
- 対象:生後6か月~60か月(5歳)までの乳幼児
- 条件:通常38℃以上の発熱に伴って出現する発作性の症状(けいれん性・非けいれん性の両方を含む)
- 除外:髄膜炎・脳炎などの中枢神経感染症や代謝異常、てんかんの既往がある場合は除外されます
つまり、熱が原因で一時的に脳の活動が乱れて起こる発作で、明らかな脳の病気がないものを「熱性けいれん(熱性発作)」と呼びます。
● 単純型と複雑型の分類
熱性けいれんは以下のように分類されます。
単純型熱性けいれん:
- 15分未満の発作
- 左右差のない全身性の発作
- 1回の発熱につき1回のみの発作
複雑型熱性けいれん:
- 焦点性(左右差や局所に偏った症状がある)
- 15分以上続く
- 24時間以内に2回以上繰り返す
● 複雑型=要注意?
これらの「複雑型」の特徴を持つ熱性けいれんは、過去の研究から将来のてんかん発症リスクと関連する事がよく知られています(N Engl J Med. 1976; 295: 1029–1033)。
ただし、これらの定義は発作の“出方”のみを基準にしており、年齢や家族歴などは含まれていません。また、複雑型であっても大多数はその後てんかんを発症しないことも、きちんと理解しておくべきポイントです。
さらにいえば、「焦点性」は発作中に体の一部に強く出る動きや左右差が見られることを指しますが、実際居合わせた現場でその判断は難しいことも多いです。
● 解熱薬は熱性けいれんの再発を防ぐ?
現在のガイドラインでは、解熱薬が熱性けいれんの再発を予防するという明確なエビデンスはないとされています。
つまり、「再発を防ぐために解熱薬を使う」という目的では推奨されていません。あくまでも発熱による不快感を和らげることや、保護者の不安を軽減する目的での使用が位置づけられています。
また、「解熱薬を使ったことで熱がぶり返して再び痙攣するのでは?」という懸念についても、そのような関係を示す根拠はないとされています。
● 発熱時にジアゼパムを使うべき?
ジアゼパム(抗てんかん薬)の坐薬や内服は、熱性けいれんの再発予防には有効性があるとされていますが、熱性けいれんそのものが多くの場合良性であること、薬の副作用(傾眠やふらつきなど)のリスクもあることから、ルーティンで使用する必要はないとされています。
「どうしても不安が強い」「何度もけいれんしている」など、医師と相談のうえで使うケースはありますが、必要性と副作用のバランスを見て検討されるべきとされています。
● 再発と予防について
- 熱性けいれんは約30%(3人に1人)で再発するとされています
- けいれん予防のために薬を日常的に服用することは基本的に推奨されていません
- 重要なのは「次に起きても慌てないための知識と準備」をしておくことです
熱性けいれんは多くの場合、予後良好な良性の発作です。しかし、「初めて起きた夜」は、親としては本当に怖い体験になります。正しく知って、落ち着いて対応できる準備をしておくことが大切だと改めて感じました。
③ 我が家で参考にしたこと|「“もしもの夜”を振り返って」
あの夜のことをきっかけに、私たちは家族としてできることを少しずつ準備してきました。
まず、発熱があったときは、その体温の推移と子どもの様子をLINEで共有するようにしました。どんなときにぐったりしていたか、けいれんが起きた時間帯はどうだったか、次の発熱に備えて振り返るための記録です。
また、痙攣が起きたときには、無理のない範囲で動画を撮ることも選択肢にしています。最優先はもちろん安全の確保ですが、医師に見せられる情報があることで診断の助けになると知ったからです。
さらに、保育園とも「けいれん時の対応」について定期的に話し合っています。連絡のタイミングや、園での対応の流れを確認しておくことで、保育中に起きた場合でもお互いに安心できます。
📌 さいごに
「熱性けいれん」は怖い。でも、怖いのは“情報がない状態で判断を迫られる”こと。
経験したからこそ、次に向けた準備ができるようになりました。
📚 引用・参考文献
- 日本小児神経学会監修. 熱性けいれん(熱性発作)診療ガイドライン2023. 診断と治療社, 2023年.
- Nelson KB, Ellenberg JH. Predictors of epilepsy in children who have experienced febrile seizures. N Engl J Med. 1976;295(19):1029-1033.


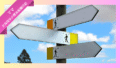
コメント