「ただ立ち上げるだけで、こんなに学びがあるとは思いませんでした。」
引っ越し・転園・転職活動に追われる暮らしの中で、私は早朝と保育園の時間を使ってWordPressブログを開設しました。これは“手順書”ではなく、転勤ママが初心者として実際にやってみて気づいたことの記録です。
なぜWordPress?|続けられる形で、深く刺さる発信を
私は文系大学院卒で、文章を書くことが好きです。何事も継続が大切だから、嫌々続けるよりも、楽しく続けられる形=ブログを選びました。SNSのように一気に広まるわけではないけれど、「必要な人に深く届く」コンテンツを作りたかったからです。
もうひとつの理由は現実的です。これまでプライベートでやってきた情報収集や整理を、ブログという“仕事”に載せ替えれば、次の転園先の就労条件を満たしやすくなります。生活の負担を増やさずに、発信を暮らしに組み込める——その土台としてWordPressを選びました。
学習面でも相性がよかった。デイトラでWeb制作を学んでいたので、「自分の手で触ってカスタマイズできる余地」があるWordPressは最適でした。丁寧に育てれば資産になり、将来のポートフォリオにもなります。
立ち上げてみての正直な感想|技術よりも「方向性」に時間がかかった
操作は思ったよりスムーズでした。ドメイン取得・サーバー契約・SSL・テーマ設定は、YouTube(特にリベ大の開設動画)を見ながら進め、デイトラで基礎を触っていたおかげで迷子にならずに済みました。
むしろ時間がかかったのは「ブログの方向性」です。テーマが曖昧だと筆が進まない。自分の生活と学びをどう結び直せば独自性が出るのか、ノートに書き出しては消してを繰り返しました。たどり着いた答えは、夫婦それぞれの視点を並走させる“夫婦ブログ”という形。ここで一気に記事が書きやすくなりました。
初心者でも掴めた学び|ユーザー視点がテンプレートタグを腑に落とす
机上では理解しづらかったことが、ユーザーとして使うと一気に腑に落ちる——これが最大の気づきです。たとえばWordPressのテンプレートタグ。教材では「何のためにあるのか」ピンと来なかったのに、実際に運用すると、「あ、この表示はデフォルトだと足りない」「この並び替えができない」という“困り感”が具体化します。そこで初めて、「だからこのタグ(機能)が必要なんだ」と腹で理解できました。
また、他のブログを見る目も変わりました。外観(テーマ)と内容(編集方針)の軸が通っているサイトは強い。デザインやレイアウトの真似ではなく、「誰に何を届けるのか」までを自分のサイトにインプットするつもりで分析するようになりました。
一方で、テーマの外観そのままでは機能に限界がある場面も。本当はゼロから作りたい気持ちもありましたが、時間資源を踏まえ、今回は「外観に内容を合わせる」方針で割り切りました。
両立のコツ|“面倒”を“必要”に変える編集脳
作業時間は早朝と保育園の時間。MacBook Proにデュアルモニター、キッチン横の小さなワークスペース——生活動線のすぐそばに机を置くと、「立ち上がってすぐ座る」が習慣化します。
もうひとつ効いたのは、何でも記事前提で動く編集脳です。引っ越し、転園、転職活動……これまで「面倒だな」と思っていた作業を、「情報を集め、検証し、記録する」という手順に変換。すると、徒労感が消え、家族にも読者にも役立つ“コンテンツ”に変わる。ブログが暮らしの駆動力になりました。
実務に直結した小さな工夫
Notionでゴール→週→日タスクを分解し、スプレッドシートに学習・作業ログを記録。「今日はここまで進んだ」を可視化すると、早朝2時間の積み上げでも前進が見える。迷いが減り、続けやすくなります。
これからのこと|テーマは割り切り、発信で差をつける
当面はCocoonなど既存テーマをベースに、中身(編集方針・導線・更新のリズム)で差をつけます。余白時間で少しずつカスタマイズに踏み込み、いずれはゼロからテーマを組める力を——。ブログは学びと生活と仕事を束ねる“自分の土台”として育てていきます。
まとめ|初心者でも、暮らしに乗せれば前に進める
初心者の私でも、生活のリズム(早朝・保育園)×買い切り教材(デイトラ)×編集脳の三点で前に進めました。技術の壁よりも難しかったのは、方向性・全体像・導線を決めること。ここに時間をかける価値があります。
WordPressは、転勤や子育てで時間が切り刻まれる生活でも、自分の歩幅で積み上げられる場所です。立ち上げて終わりではなく、立ち上げた先にこそ学びがある。私はその最初の一歩を、ようやく踏み出せました。

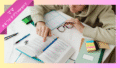
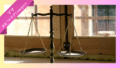
コメント